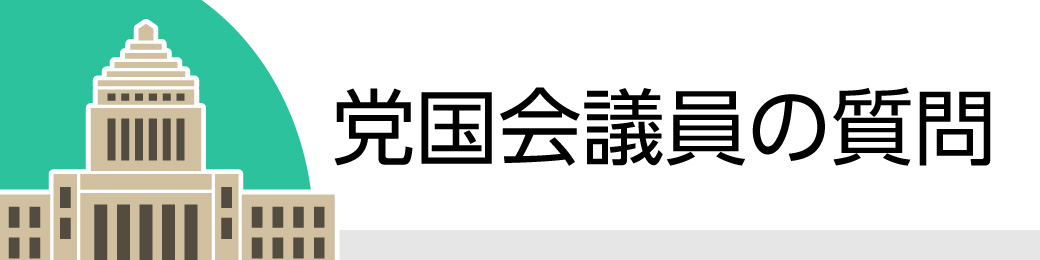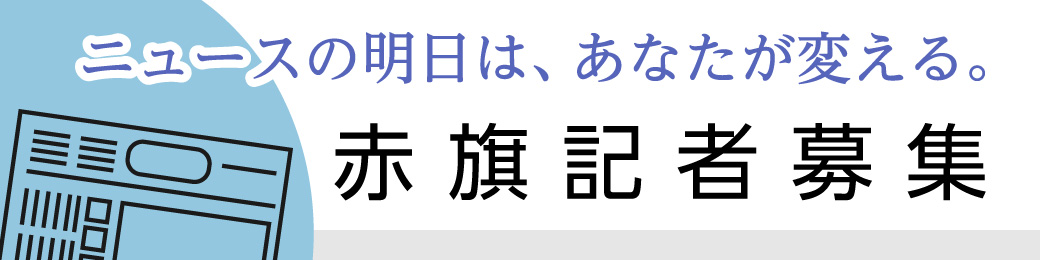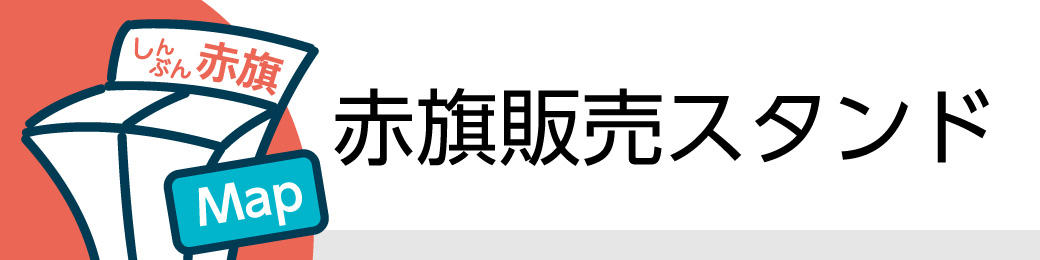2025年3月28日(金)
建設労働者が誇りをもって働ける日本を
志位議長の講演から
22日、党本部と全国をオンラインで結んで開かれた、全国建設労働者日本共産党後援会主催の「志位和夫議長になんでも聞いてみよう――建設労働者と語り合うつどい」での志位議長の講演から、建設労働者の労働条件をどうよくするか、世界と日本の建設労働者の闘いの歴史にかかわる部分、最後の入党の呼びかけの部分の要旨を紹介します。
建設労働者の労働条件を改善するには何が必要か
 (写真)質問に答える志位和夫議長=22日、党本部 |
質問 週休2日制の完全実施のもとで賃上げをするにはどうしたらいいですか。建設労働者の労働条件を改善するには、何が必要だと考えますか。
志位 この間、私は、建設労働者のみなさんとさまざまな形で懇談する機会がありました。その後、建設労働者と建設労働組合について私なりに勉強もしてきました。あらためて、みなさんの運動が、先駆性、創意性、戦闘性を発揮して、いろいろな困難を乗り越えて発展していることに対して、強い尊敬の気持ちを持ちました。
「賃金・単価の引き上げも、労働時間短縮も、安全確保と労働環境改善も」の立場で
志位 労働条件という点では、建設労働者のみなさんは、大きくいって三つの要求があると思います。
一つは、賃金・単価を引き上げること。
二つ目は、労働時間を短くすること。
三つ目は、建設現場の安全を確保し、労働環境をよくすることです。
それぞれがたいへんに切実な願いであり、あれかこれかではなくて、そのすべての実現を勝ち取るための闘いをともに進めたいと思います。
建設労働者のみなさんは、本当に大きな社会的役割を果たしていると思います。住宅の建設、生活インフラの整備、災害の復旧・復興、日本社会を土台から支え、発展させるためのかけがえのない仕事をしています。
ところが、建設労働者の賃金は全産業平均に比べて10%低い。労働時間は17%長い。完全週休2日制導入の割合は30%低い。「低賃金、長時間労働、休日の少なさ」――これが若い方が建設で働くうえで大きな障害になっていると思います。この障害を取り除いて、建設労働が魅力のある、希望の持てる仕事になるように「賃金・単価の引き上げも、時短も、安全確保と労働環境改善も」という立場でともに闘いたいと思います。
大手企業に対する企業交渉の取り組みを発展させ、「労働協約」の締結を目指す
志位 「どうしたらいいか」というご質問ですが、私が、みなさんの運動から学んで大切だと考えていることを話したいと思います。
昨年5月、「第3次担い手3法」が成立しました。適正な賃金を確保し、長時間労働の抑制をはかる法律です。「持続可能な建設業実現に向けた100万人署名運動」など、みなさんの闘いが勝ち取った重要な成果です。ただ、労働者の処遇改善は「努力義務」となっており、これをどうやって実効あるものにしていくかは、これからの闘いの大きな課題だと思います。
私は、この点で、みなさんが闘って切り開いてきた「二つの努力方向」をさらに発展させていくことが大切ではないか。私たちも、ともに力をつくしたいと思います。
一つは、大手ゼネコンや大手住宅メーカーに対する企業交渉の取り組みを発展させ、賃金や労働時間を含む労働条件を決める「労働協約」を締結することを目指すということであります。
建設労働組合のみなさんは、1980年代から大手企業交渉を進め、労働条件をよくするさまざまな取り決めを勝ち取ってきています。たとえば、みなさん方の資料を拝見しますと、昨年、東京では、大手企業交渉が、大手ゼネコン、大手住宅メーカーなど40社以上に対して行われています。もう一つ、大切だと思うのは、2018年ごろから取り組まれている、元請け大手ゼネコンや、大手住宅メーカーとの間で、「パートナーシップ協約」――労働条件改善の協約を締結する運動です。
これらの闘いを発展させて、さまざまなレベルでの「労働協約」を結んで、労働条件を決めていくというところに進んでいくことが、今後の方向として大切になってくるのではないでしょうか。労働条件という点では、賃金と単価、労働時間、労働環境改善などとともに、給与の形態の改善なども大切だと思います。「日給月払い」という給与形態がまだ少なくありません。この場合、週休2日制になると賃金が下がってしまう。「月給固定制」にする必要があります。そういうことも含めて「労働協約」で決めていく。
私たちは、政治の責任としては、大手企業によるピンハネを規制して、元請け責任を現場までしっかり果たさせる、より実効ある法律、またそれを実施させる監視体制をみなさんと一緒につくっていきたいと考えています。
公契約条例を広げ、公契約法をつくる運動をともに前進させよう
志位 もう一つの努力方向は、みなさんが2001年以来取り組んでいる、公契約条例を広げ、公契約法をつくる運動です。調べてみますと、直近のデータで、全国で公契約条例を制定しているのは90自治体にのぼります。東京では19の市区でつくられています。国との関係では、公契約法の制定が必要です。この取り組みを力をあわせて前進させていきたいと思います。
東京都議会議員選挙に向け、日本共産党は、都として公契約条例をつくることを提案しています。いま、都が発注している仕事は1・7兆円にのぼります。ここで働く人の賃金、労働条件の改善をはかろうというのが、わが党の提案です。
建設労働者の闘いの力と、政治を変えることの両方で、労働条件の改善を勝ち取ろうということを呼びかけたいと思います。(拍手)
現場労働者、一人親方、小規模事業主でつくられる労働組合――どういう闘い方が大切か
質問 建設労働組合は、現場労働者、一人親方、小規模事業主など、多様な働き方の組合員で構成されています。賃上げの交渉相手が同じ組合員である場合もあります。どういう闘い方が大切だと思われますか。
志位 日本の建設労働組合は、大まかに言って、現場労働者、一人親方、小規模事業主などで構成されています。
一人親方や小規模事業主が、現場労働者と同じ労働組合に参加して、肩を並べて闘っている労働組合は、日本にしかありません。世界に日本だけのユニークなものですが、私は、ここに日本の建設労働運動の大きな強みがあると思うんです。
相手をしっかり見据え、すべての労組構成員の「連帯と団結」を強めて
志位 「どういう闘い方が大切か」というご質問ですが、一言で言いますと、すべての労組構成員の「連帯と団結」を強め、組織を大きくする。ここにあると思います。
現場労働者も、一人親方も、小規模事業主も、建設労働に従事している労働者であることに変わりはありません。そして、大手ゼネコンや大手住宅メーカーを頂点とした重層的な下請け構造のもとで苦しめられているという点でも、変わりはありません。
すなわち、闘うべき相手は、共通の相手です。大手ゼネコンや、大手住宅メーカー、さらに国や自治体が相手になってきます。たとえば、大手住宅メーカーがどれだけもうけているか。大和ハウス、積水ハウス、住友林業の最大手3社だけで、この10年間に、利益を2044億円から6036億円に、3倍にも増やしています。大手住宅メーカーは、みなさんから絞り上げて、空前の利益をあげているわけですから、賃上げは当然、時短も当然です。その責任を果たしてもらう。相手をしっかり見据えて、すべての労組構成員の「連帯と団結」を最大の力にして闘うことが何よりも重要ではないかと思います。
使用者に対し労働者の要求実現を求めるとともに、力をあわせ大手企業の横暴と闘う
志位 闘い方という点では、建設労働組合の闘いは、中小企業における労働組合の闘いと共通点があるように思います。
日本の中小企業の多くは、大企業の重層的下請け構造のもとに置かれていたり、大企業と不公正な取引を強いられるなど、財界・大企業によってさまざまな経営困難が押しつけられています。たとえば、トヨタの場合、下請け構造は、1次、2次、3次、4次……と続き、「乾いたタオルを絞る」といった過酷な締め付けがされています。
ですから中小企業における労働組合は、二重の闘いが必要になってきます。一つは、使用者に対して労働者の要求実現を求めて奮闘する。もう一つは、中小企業に経営困難をもたらしている大企業の横暴と闘うことです。そうした二重の闘いが大切になってくる。
建設労働組合の場合も、使用者に対して労働者の要求と権利の実現を求めていくことは当然大切になります。同時に、使用者が小規模事業主の場合、同じ組合員ですから、組合員の経営を守るために、共通の闘うべき相手である大手ゼネコンや、大手住宅メーカーに対して、力をあわせて団体交渉を行って、要求実現をはかっていくことが大事になると思います。実際に、そうした闘いをやっているのが、みなさんの運動だと思います。
もう一つの相手が、国と自治体です。国や自治体に対して、公契約条例や公契約法を制定せよ、建設国保を強化せよ、リフォーム助成をつくれなどのさまざまな制度要求、政策要求の実現を迫っていく。
こういう闘いを、すべての労組構成員の「連帯と団結」の力で進めていこうと呼びかけたいし、私たちも一緒に闘っていきたいと思います。
そして、このなかで、政治を変える闘いを訴えたい。元請け大企業の横暴を抑えるルールをつくる、公契約条例や公契約法をつくる、さらに消費税の減税を実行し、インボイスを廃止し、健康保険証の取り上げをやめさせる。どれも政治を変える闘いが必要になってきます。そのためにも日本共産党をどうか都議選・参院選で勝たせてほしいということを訴えるものです。(拍手)
世界と日本の建設労働者の闘いの歴史について
質問 志位さんは千葉市での講演で、マルクスがロンドンの建築労働者の闘いに注目したことを話されました。さらに突っ込んで話していただければと思います。また、日本の建設労働者の闘いの歴史について、どうご覧になっていますか。
マルクスは、ロンドンの建築労働者の大ストライキを研究し、連帯の論陣をはった
志位 千葉市での「労働者のつどい」でお話しするさい、私たちの大先輩であるカール・マルクスと建築労働者との交流と連帯について、あらためて調べてみました。そうしますと、たいへんに深い交流と連帯をやっている。
マルクスは、1850年代後半から60年代前半にかけて『資本論』を準備するノート、『資本論草稿』を執筆していきます。この時期、1860年に、ロンドンで建築労働者が、9時間労働制と賃上げを求めて大ストライキ闘争に立ち上がりました。マルクスは、このストライキに注目して、詳しい研究を行うとともに、連帯の論陣をはっています。
当時のイギリスでは、建築業の規模と比重が大きく、建設労働組合が労働組合の中で重要な地位を占めていました。1864年、インタナショナル(国際労働者協会)という、世界で初めての労働者の国際的な組織がつくられます。インタナショナルの執行部に、大ストライキ闘争に参加した建築労働者が入っていて、マルクスは建築労働者と親しい交流をしているんです。
『資本論』を読みますと、1860年の大ストライキに注目して、高く評価する叙述が出てきます。「時間賃銀を押しつけようとする資本家たちの企てに反対して、建築業に従事するロンドンの労働者たちが蜂起した(1860年)のは、まったく理にかなったことであった」(新版『資本論』③、948ページ)。『資本論』の叙述を準備した『資本論草稿』では、ロンドンの建築部門の労働者と資本家との闘争について、ひとまとまりの論考を書いています。そして、建築労働者の闘いを研究した叙述の前後に、労働者が「自由な時間」を拡大することの意義が考察されていることは、たいへんに重要だと思います。
「自由な時間」を取り戻そう――労働時間を短縮して自らの解放を勝ち取ろうというマルクスの呼びかけは、ただ頭の中で考えたものではありません。建築労働者の大ストライキ闘争をはじめ、労働者の闘いを研究し、連帯する中でつくっていったものでした。『資本論』は、そういう労働者の闘いがつまった本でもありますので、ぜひ学び、広げていただきたいと思います。
石工組合のストライキ、建設国保を獲得・強化してきた闘い
志位 それでは、日本の闘いはどうでしょうか。日本の闘いの伝統もすごいものがあります。私は、この間、昨年(2024年)1月に発刊された『東京土建の75年 歴史と教訓 1947年~2022年』を読む機会がありました。建設労働者が、いかに戦前・戦後の闘いで自らの権利を獲得し、拡大してきたか、生きた闘いの歴史が叙述されています。たくさん感動するところがありましたが、二つほど話したいと思います。
まず戦前です。1931年、山から石を切り出して建物をつくる石工(いしく)の組合、東京石工組合の二千数百人が2カ月におよぶ全市ストライキを決行したことが叙述されています。親方組合に対して、賃金引き下げ反対、組合の民主化を掲げて闘った。この全市ゼネストによって、新築中の国会議事堂をはじめ、石材加工現場には1人の石工の姿もなくなったとのことです。当時、親方組合は、“二分五厘”という暴力団とも深いつながりがあるゴロツキを置き、現場を暴力的に支配していた。これをやめろと、文字通り命懸けの闘いをやったということです。このゼネストによって、賃金の面でも、組合の民主化の面でも、重要な成果を勝ち取りました。この闘いの中心になって頑張った方々が、戦後の建設労働組合の誕生と発展に大きな役割を果たしたとのことです。
戦後、印象深い闘いがたくさん叙述されていますが、1953年、日雇健康保険の獲得はとても大きな出来事だったと思います。「ケガと弁当は手前持ち」といわれた建設労働者にとって、労災保険、健康保険の適用は戦前からの切実な要求でした。戦後も、「ケガと弁当は手前持ち」という生活が続き、職人は親方に隷属した関係におかれ、病気になったときにも、親方に金を借り、親方の世話になるという状態だった。こういう状態を打破して、自分たちで保険をつくろうではないかと、日雇健康保険を獲得した。このことが職人が親方から自立し、誇りを獲得していく重要な第一歩になりました。それが建設国保になって発展していく。建設国保は激しい攻撃にさらされましたが、いまなお、国庫補助を確保してそれを育成・強化する闘いが続いています。建設労働者のみなさんと懇談したさい、「闘いによって勝ち取った権利は絶対に手放さない」と言っていました。本当にその通りだと思って、聞きました。
闘いによって労働者としての自らの誇りを獲得してきた歴史
志位 『東京土建の75年』を読んで、建設労働組合の歴史は、闘いによって三つの先駆的な特質をつくりあげてきた歴史だと感じました。
第一は、団体交渉によって労働条件をよくする。
第二は、政府や自治体に働きかけて法律や条例をつくっていく。
第三は、保険と相互扶助によって暮らしを守る。
労働組合として保険と相互扶助に取り組むというのは、ヨーロッパではどこでもやっていることですが、日本ではそうなっていない。そのなかで建設労働組合が、建設国保をみんなの力でつくり発展させてきた。これはすごいことです。
この三つの特質があると思います。私は、この歴史はまた、闘いによって労働者としての自らの誇りを獲得してきた歴史だと痛感しました。これは誇るべき到達ではないかと思います。
世界でも日本でも、労働者の闘いこそ歴史をつくる力であり、労働者の権利と生活を守る力です。そして建設労働者は、世界でも日本でも労働者階級の闘いの先頭に立って頑張ってきた歴史を持っています。ぜひ、そのことに誇りを持って、みなさんの運動を発展させていっていただきたいと思いますし、建設労働者の中で日本共産党を大きくする仕事にも、どうかご協力いただきたいと心からお願いいたします。(拍手)
日本の世直しのために日本共産党に入ろう
志位 最後に、一言呼びかけをいたします。日本の世直しのために、どうか日本共産党に入党していただきたいということです。
建設労働者のみなさんが誇りを持って働ける社会をつくるためには、いまの日本の政治を大もとから変える必要があります。
――大企業の横暴を抑える「社会的ルール」をつくり、「財界・大企業中心」の政治のゆがみをただす世直しをすすめること。
――「異常なアメリカいいなり」の政治のゆがみをただし、外交の力で平和をつくる世直しをすすめること。「建設労働者の腕や知識は絶対に戦争に利用させてはならない」というみなさんの先人の言葉がいよいよ大切であること。
こうした世直しを進めるためには、日本と世界を科学の力で見通して、どんな困難があっても頑張りぬく日本共産党を大きくすることがどうしても必要です。職場で日本共産党員を増やすことが、労働運動の階級的・民主的強化につながっていきます。どうかこの機会に日本共産党に入って、建設労働者のみなさんが誇りと希望を持って働ける日本を一緒につくろうではないか、ということを呼びかけて、終わりにしたいと思います。(拍手)