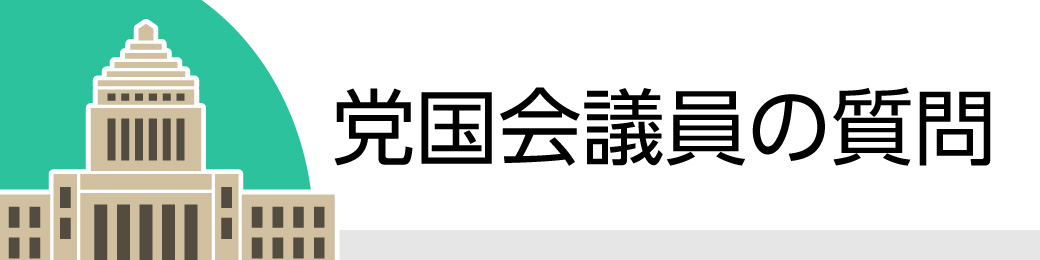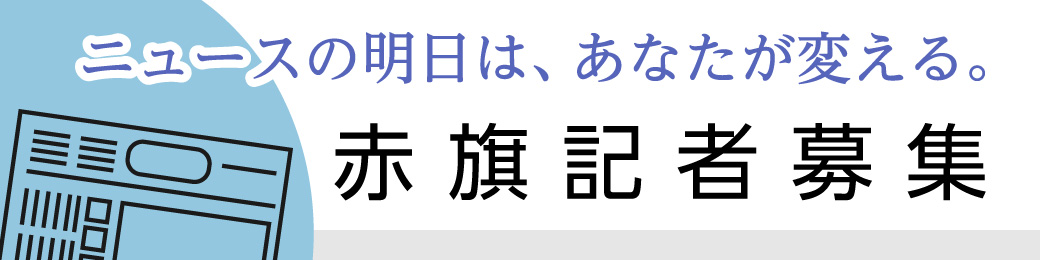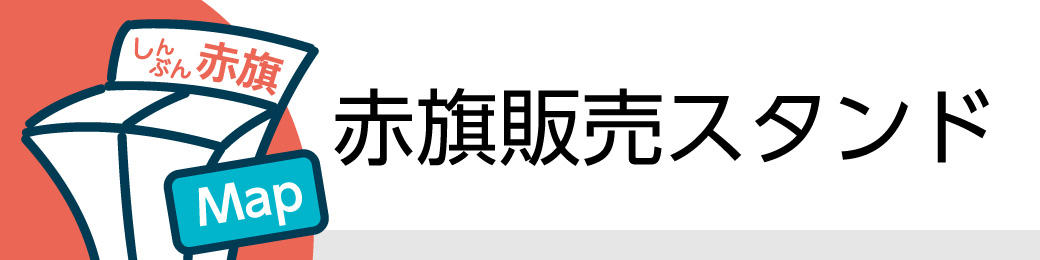2025年3月28日(金)
主張
普通選挙と治安維持
主権者を閉め出してどうする
100年前の3月29日、帝国議会で、納税額による制限を撤廃し、25歳以上のすべての男性に選挙権を与える普通選挙法が成立しました。その10日前に成立した弾圧立法・治安維持法と対をなすものとして知られています。
労働者、農民に選挙権を与えることに不安を覚えた天皇制政府は、治安維持法によって凶暴な弾圧態勢を強化するとともに、普選法では選挙活動にそれまでなかった厳しい規制を加えました。
■戦前残す選挙規制
問題はその規制が今日の公選法にそのまま引き継がれていることです。
公選法は、戸別訪問を禁止し、ビラ、ポスターの配布規制など選挙活動についてさまざまな制限を加えています。 しかし、選挙で運動員やボランティアが戸別訪問し、有権者一人ひとりと政治について対話する活動は、国際的には当たり前のことです。
米国の大統領選挙では運動員が熱心に戸別訪問し、対話していることは日本でもよく報じられています。先日のドイツ総選挙で躍進した左翼党は、ベルリンのある小選挙区で全世帯の半数に戸別訪問を行いました。
民主主義社会を支える選挙の基本的な活動を禁止しているのが、日本です。
「市民と野党の共闘」で戦われた2016年の参院選では多くの市民が初めて選挙活動に参加しました。戸別訪問禁止やビラに候補者名を記載できないなどの規制にぶつかり、「なぜ選挙中に選挙活動が禁止されるのか」という驚きの声があがりました。
国連も日本の選挙活動の制限に警告を発しています。国連自由権規約委員会は「戸別訪問の禁止や選挙活動期間中に配布することのできる文書図画の数と形式に対する制限など、表現の自由と政治に参与する権利に対して加えられている不合理な制限に、懸念を有する」と表明。「表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」と勧告しています(08年)。
元自治省選挙部長の片木淳弁護士は、治安維持法とセットで普選法の活動規制が生まれたのは、「無産運動などが高まるもとで、一気に有権者が4倍化し、1200万人にも膨らむことへの警戒感があった」と指摘、戸別訪問禁止などは「天皇主権のもとでの規制だったわけで、戦後、撤廃されるべきでした。…この分野には『戦前』が残っているのです」(『時代を拓〈ひら〉くあなたへ』)と厳しく批判しています。
■国民の権利の行使
選挙権の行使は主権者である「国民固有の権利」(憲法第15条)です。選挙の主人公たる国民の自由な選挙活動を妨げている規制をなくしてこそ、憲法上の権利である参政権を行使できます。世界的に見ても異常な規制で主権者を閉め出すことは許されません。
国民の口をふさぎ、手足をしばる選挙活動規制は戦前の天皇制政治の遺産です。国民が主権者として、自らの代表を選び政治に積極的に参加していくため、選挙に気軽に参加できるように、公選法を抜本的に見直すときです。