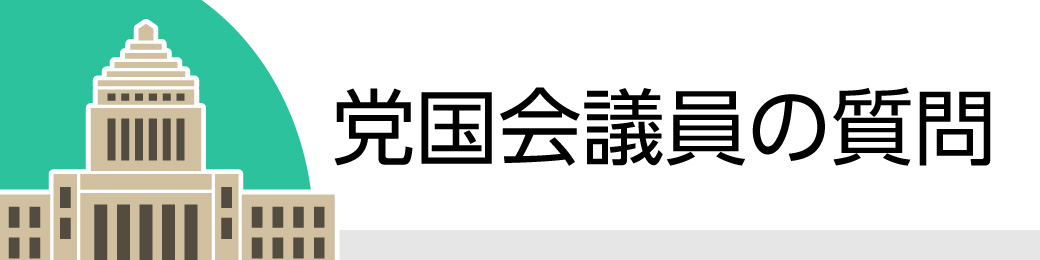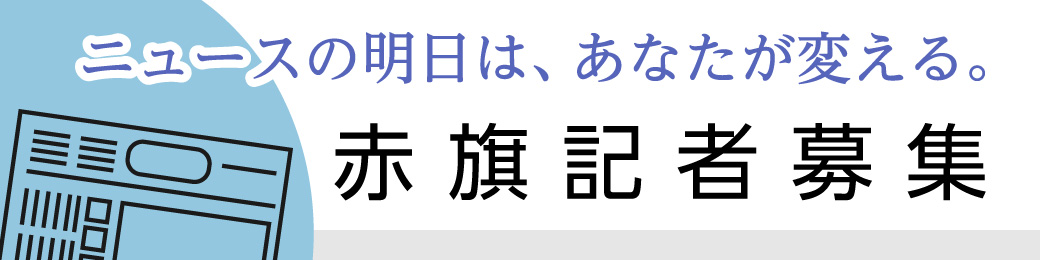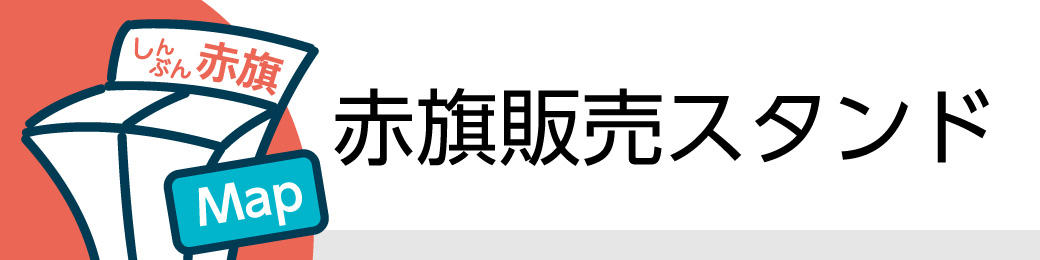2025年1月29日(水)
田村委員長の代表質問 衆院本会議
日本共産党の田村智子委員長が28日の衆院本会議で行った、石破茂首相の施政方針演説に対する代表質問は次の通りです。
自民裏金事件の幕引きは許されない
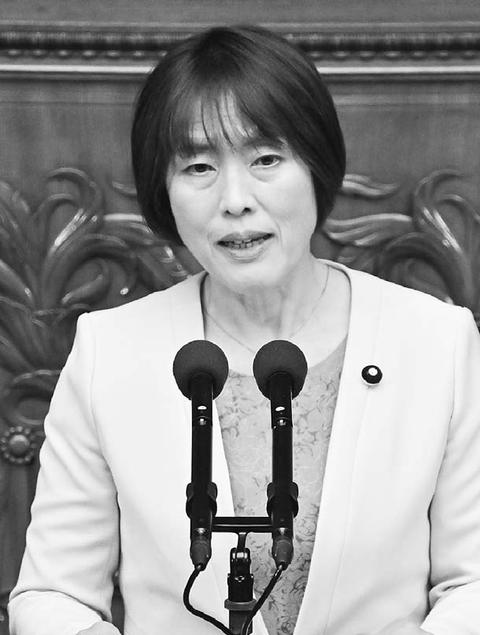 (写真)質問する田村智子委員長=28日、衆院本会議 |
私は日本共産党を代表し、石破首相の施政方針演説に対して質問いたします。
まず、昨年の臨時国会からの宿題、「政治改革」です。
総理、自民党の裏金は「終わったこと」なのでしょうか。与党過半数割れの最大の要因は、裏金への国民の審判です。ところが、総理の施政方針演説に一言もなかったのはなぜですか。この間、政治倫理審査会が相次いで行われましたが、自民党議員の弁明は“事務局や秘書がやったこと”という開き直りに終始し、安倍派会計責任者の裁判での証言とも矛盾したままです。世論調査を見ても、「事実は明らかになっていない」「真相究明すべき」というのが、多くの国民の思いです。総理、裏金づくりがいつから誰の指示で始まったのか、何も明らかにならないまま「幕引き」することは許されないと考えますが、いかがですか。関係者の証人喚問による真相解明を強く求めます。
「しんぶん赤旗」日曜版のスクープが契機となり、都議会自民党の裏金に捜査が入り、会計担当職員が立件されました。日本共産党都議団が入手した自民党の内部文書には、2019年の政治資金パーティーについて、都議会議員1人あたり100枚のパーティー券を配布、納入は50枚分100万円と書いてあります。あらかじめキックバックがシステム化されていたのではありませんか。また「都連所属衆参議員46名、1人30枚配布」とあり、東京選出の自民党国会議員がどう対応したのか、都議会自民党の違法行為を知らなかったのか等、新たな疑惑も浮上しています。都議会自民党の裏金についても徹底的に調査し、裏金の全容を明らかにすることなしに、国民の信頼回復はありえません。総理、お答えください。
「政治改革」の根幹、企業・団体献金の全面禁止を
政治改革の根幹は、企業・団体献金の全面禁止です。
そもそも「企業献金は本質的にわいろ性をもつ」と、わが党は繰り返し示してきました。日本経団連は、2004年度から、自民党の野党時代を除いて今日まで、政策要望と一体に「自民党の政策評価」を事細かに行い、企業献金のあっせんやよびかけを行ってきました。
例えば「法人税の実効税率引き下げ」「租税負担と社会保障負担を合わせた企業の公的負担を抑制する」、これとあわせて「消費税率の引き上げを検討する」こと。この要望は2004年度から繰り返し行われ、自民党がどこまでこたえているかを毎年評価し、自民党への企業献金が行われてきたのです。
法人実効税率は、40・87%から、今や29・74%にまで引き下げられました。消費税は5%から10%へと引き上げられ、社会保障予算は必要額が削減され、医療・介護の国民負担が大幅に増えました。まさに消費税増税と一体で、「租税負担と社会保障負担を合わせた企業の公的負担を抑制」する政策が、国民の反対の声を聞かず、日本経団連の要望の通りに進められた、これが事実ではありませんか。
今や国民多数が「企業献金禁止」を求めています。それでもまだ自民党だけが企業献金にしがみつくのですか。それは、国民の声よりも「財界・大企業」の声を聞くと宣言するに等しいではありませんか。答弁を求めます。
総選挙での民意に応え、今国会で、企業・団体献金全面禁止を必ず実現しようではありませんか。すべての政党・会派のみなさんに呼びかけるものです。
暮らしの困難を打開し、安心とゆとりを――五つの改革を
お米も、白菜やキャベツも驚くほどの値上げで、毎日の買い物に行くのが怖い――こうした声が街の中にあふれています。今の暮らしの苦しさの根底には、「失われた30年」が続いているという大問題があります。30年間賃金が上がらず、年金は目減りし、消費税と医療・介護の負担が繰り返し増やされ、大学や専門学校の学費負担が重くのしかかり、そこに物価高騰が襲ってきた。すべては自民党政治が引き起こした人災です。この暮らしの困難を打開するには、シングルイシューの部分的改良ではとても足りず、暮らしにかかわる政策全体の転換が求められていると考えますが、総理、いかがですか。
日本共産党は、暮らしの困難を打開し、安心とゆとりのために五つの改革を提案します。
《大幅賃上げ》
第1は、大幅賃上げと労働時間の短縮を一体に進める改革です。
総理は、「大幅賃上げが実現した」と繰り返しますが、長期にわたり実質賃金が大きく落ち込んだうえ、足元でも実質賃金がマイナス傾向から脱していないという事実を直視すべきではありませんか。まずはアベノミクス以降のマイナス分を取り戻す、年33万円以上の賃上げを最低限の目標として、正真正銘の大幅賃上げを政府の方針とすべきと考えますが、いかがですか。
大企業の史上最高の利益が、賃上げにも取引企業の単価引き上げにも回らずに、ただただ内部留保が膨張を続ける――総理、このゆがみを正すことが、大幅賃上げに不可欠ではありませんか。内部留保の一部に時限的に課税して、中小企業の賃上げへの直接支援に充てるなど、たまりすぎた内部留保を賃上げに回すなどの仕組みを政治の責任でつくることこそ必要ではありませんか。
大幅賃上げと一体で労働時間を短縮する、つまり収入も自分の時間も増える働き方へ改革してこそ、ほんとうに豊かな暮らしといえます。総理、現在の長時間労働が、働く人の健康を壊し、子育てにも大きな困難をもたらしているという認識はありますか。残業規制の強化で長時間労働をなくすとともに、労働時間短縮へと進んでこそ、ジェンダー平等が実現すると考えますが、総理の認識をお聞きします。
《税制改革》
第2は、不公正な税制を抜本的にただす改革です。
毎日の生活のための最低限の費用には課税しない、この生計費非課税の原則に立つことが、暮らしの応援にも、公正な税制のためにも必要ではありませんか。明確にお答えください。
課税最低限の引き上げは当然ですが、103万円に届かない3000万人には何の恩恵もありません。最も困っている人に届く政策として、消費税こそ廃止をめざしただちに減税し、インボイスを廃止すべきです。大企業の法人税をアベノミクス以前の税率に戻し、大企業・富裕層への税優遇をただせば14・6兆円の税収が見込まれ、消費税5%への引き下げは十分に可能です。これこそ公正な税制により暮らしを応援する確かな改革ではありませんか。答弁を求めます。
《社会保障》
第3は、すべての世代を支える社会保障への改革です。物価が上がれば増える年金への改革、医療・介護の基盤崩壊を止める、ケア労働者の抜本的な処遇改善を求めます。
「現役世代の負担軽減」といって、年金・医療・介護の制度改悪を繰り返せば、現役世代にも負担と不安を広げることになります。事実、来年度予算案では、高額療養費の負担上限を引き上げて、「保険料負担の抑制につなげる」としていますが、がん患者など重症患者に負担増をもたらすことが、どうして、社会保障への不安の解消につながるのでしょうか。ただちに撤回することを求めます。
いま「対立」しているのは「高齢者と現役世代」では決してありません。企業献金をテコに、企業の税と社会保障の負担軽減を求めてきた財界・大企業、それに唯々諾々と従ってきた自民党政治と国民こそが「対立」しているのではありませんか。税と社会保障の応分の負担を大企業に求め、医療、介護、年金への公的支出を増やしてこそ、すべての世代にとって安心の社会保障を実現できると考えますが、総理、いかがですか。
特に、訪問介護をはじめ介護の基盤崩壊は、人口の少ない地域ほど深刻です。総理、地方創生というのなら、ただちに訪問介護の基本報酬をひきあげるとともに、介護保険に対する国の負担割合を増やすべきではありませんか。
《学費値上げストップ、教育費負担ゼロ》
第4は、学費・教育費負担ゼロへの改革です。
国公私立大学の4割が、来年度の授業料値上げを実施あるいは検討中――日本経済新聞の報道に衝撃が走っています。総理、いまでも大学の学費は、学生と保護者にとって重い負担であり、子育て世代の強い不安となっている、このことを認めますか。
驚いたのは、来年度予算案で国立大学運営費交付金を据え置いていることです。国立私立ともに経常経費への交付金、補助金は長期にわたって削減され、そこに物価高騰が襲いかかっているのです。これでは学費値上げを促進するに等しいではありませんか。来年度の大学授業料値上げを止めるために1000億円の緊急助成、そしてOECD(経済協力開発機構)で最低水準の教育予算を抜本的に増額し、値下げ、学費ゼロへと向かうべきではありませんか。学校給食の無償化、高校の学費ゼロをふくめ、教育費負担ゼロへ、また、教員の長時間労働を解決する大幅増員へ、教育予算の思い切った拡充を求めるものです。
《食料安定供給、持続可能な農業》
第5に、食料の安定供給、持続可能な農業への転換です。
総理、38%にまで落ち込んだ食料自給率の目標をどうするのですか。まず、50%への引き上げを目標として、その達成への責任ある政策を示すべきではありませんか。
これまでの大規模化一本やりでは農家・農地の急速な減少も、酪農家の廃業も止めることはできません。家族的経営を含め、すべての農業、酪農、畜産の従事者の所得を増やす政策に転換する――これは地方創生にとっても、国民への食料安定供給にとっても喫緊の課題だと考えますが、いかがですか。
《大軍拡・大企業奉仕の放漫財政にメスを入れる》
日本共産党は、以上のべた暮らしの全体を応援する政策を、財源とともに提案しています。大企業・富裕層への応分の負担によって税収を確保し、大軍拡の中止、大企業の利益最優先の事業の見直しにより、消費税減税、社会保障、教育など恒常的な予算を確保する、災害、物価高騰対策など一時的に国民のために必要な場合には国債発行を行う――これらで40兆円規模の財源を暮らしに充てることが可能です。政策は財源の裏付けと一体で議論する、これは国民に対する責任だと私たちは考えますが、総理の認識をお示しください。
この点で、来年度予算案はどうでしょうか。軍事費は8・7兆円、補正予算を含めこの3年間、毎年、1兆円を超えて増え続ける。総理、いったい財源をどうするのですか。庶民増税、暮らしの予算の切り捨て、国債の大量増発しかなくなるのではありませんか。
その中身も、米軍と一体に、外国を攻撃するための長射程ミサイルの実戦配備など「戦争の準備」そのものです。総理は、「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している」と繰り返し述べていますが、長射程ミサイルを大量に配備すれば、戦争の心配は無くなるのでしょうか。むしろ軍事対軍事の悪循環をエスカレートさせるのではありませんか。ASEANと協力して、東アジアのすべての国を包摂する対話、外交によって、戦争の心配のない東アジアを構築する――日本共産党の「東アジア平和提言」について、総理の見解をお聞かせください。
来年度予算案は、個別の半導体企業に補正と合わせて1・3兆円もの公費を投入するなど、大企業への大盤振る舞いも目に余ります。能登の災害に対して被災者生活再建支援金の増額も対象拡大もやらない、中小企業への賃上げ直接支援もやらない、しかし個別大企業には惜しみなく資金を投じる、あまりにもゆがんだ予算案ではありませんか。
日本共産党は、大軍拡と大企業への放漫財政に切り込み、暮らしを積極的に応援する財政へと予算案の抜本的組み替えを求めて奮闘することを表明するものです。
戦後80年、「日米同盟絶対」でよいのかを考えるべき
戦後80年、「日米同盟絶対」で良いのか、3点お聞きしたい。
一つは、2月に行われるとされる日米首脳会談についてです。トランプ米大統領は就任直後から、「米国第一」を最優先とし、「パナマ運河」を取り戻すと発言したり、気候危機打開の「パリ協定」からの離脱など、国連憲章・国際法にもとづく平和の秩序にも、国際協調にも背を向ける言動を繰り返しています。総理、日米首脳会談で、このようなトランプ大統領の言動に対してきっぱりと批判し、国際秩序、国際協調を尊重するよう求めるべきではありませんか。
二つ目は核兵器についてです。被爆80年、唯一の戦争被爆国として日本が何をなすのかが問われるもとで、政府は、核兵器禁止条約第3回締約国会議に参加しないと報道され、被爆者のみなさんから落胆と怒りの声が起きています。総理、オブザーバー参加すべきではないですか。参加できない理由があるならば示していただきたい。核兵器禁止条約は、被爆者が核兵器の非人道性を訴え抜いたことが力となって誕生しました。総理も、核兵器の非人道性を批判しておられる、ならばお聞きしたい。総理は、いかなる状況のもとでも核兵器の使用は許されない、この立場に立ちますか。核抑止は、いざというときには核兵器を使用することを前提としたものであり、核兵器の非人道性への批判と根本的に矛盾するのではありませんか。明確な答弁を求めます。
三つ目は、いつまで沖縄を米軍基地の島にしておくのかということです。占領軍によって奪われた土地に米軍基地がつくられ、米兵による性暴力にどれだけの女性・少女そして子どもが犠牲になってきたか。重大事故、騒音被害など、沖縄は80年間、平穏な暮らしが奪われています。その上、県民の民意を踏みにじる米軍辺野古新基地建設を強行することは断じて許されません。やるべきは、危険な普天間基地の即時閉鎖・撤去、日米地位協定の抜本的見直し、沖縄を平和で豊かな島にする政治への転換ではありませんか。総理の答弁を求めます。
選択的夫婦別姓の実現を
最後に選択的夫婦別姓について端的にお聞きします。総理は党内の議論を丁寧にと言いますが、自民党は30年にわたって党内協議がまとまらない、それを理由に選択的夫婦別姓の法案審議を妨げてきたのではありませんか。もう妨害をやめるべきです。「私たちを踏みつけているその足をどけてほしい」。運動を続けてきたみなさんの思いに応えて、今国会で、民法改正の法案審議に踏み出し、選択的夫婦別姓を実現することを強く求めるものです。日本共産党は国民のみなさんの要求の側に立ち、国民のみなさんの声で国会を動かし、自民党政治を終わらせるために全力を尽くす、その決意を表明し、質問を終わります。