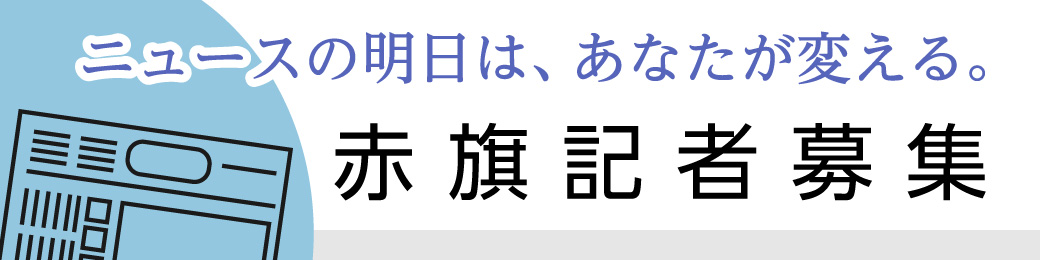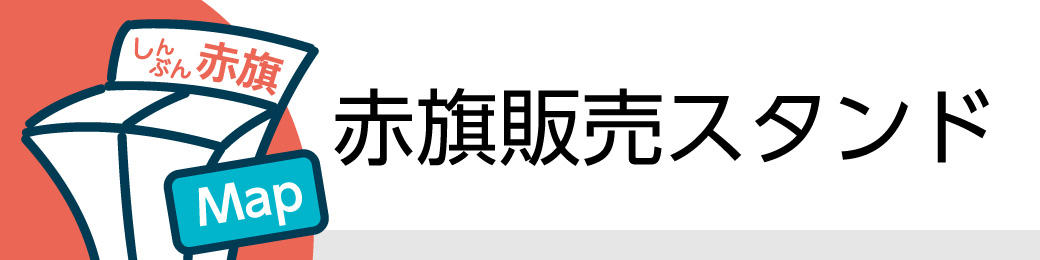2019年8月14日(水)
シリーズ 日韓関係を考える
徴用工問題 協議開始を
弁護士 川上詩朗さん
 (写真)1958年、北海道生まれ。中国人戦争被害者訴訟弁護団で平頂山事件や中国人強制連行、慰安婦問題に取り組む。「韓国併合100年」である2010年から韓国人徴用工問題にも取り組む。 |
安倍政権が徴用工問題への報復措置として、韓国に対する貿易制限の拡大に踏み切ったことで深刻化している日韓関係をシリーズで考えます。初回は弁護士の川上詩朗さんです。
日本政府による貿易制限をはじめ日韓関係の悪化は国民感情の対立にまで発展し、極めて深刻な事態です。
私は、現在の局面打開のためには、安倍政権の外交方針の問題点を検討することと同時に、事態の背景にある徴用工問題をめぐり、当事者間や政府間で問題解決へ向けた話し合いを始めることが何より重要だと思います。
安倍政権は昨年10月の大法院判決の直後から、日韓請求権協定(1965年)をたてに「解決済みだ」と繰り返し、民間での対話にも否定的です。
しかし、日韓両国の政府も裁判所も「個人の賠償請求権は消滅していない」という点では一致しています。日韓請求権協定は、被害者の賠償請求を拒む根拠にはなりません。
そもそも、徴用工問題は重大な人権侵害による被害の回復の問題です。少女や未成年者だった被害者は、アジア・太平洋戦争中に植民地支配下の朝鮮半島からだまされるなどして動員され、日本企業で賃金も支払われず過酷な労働を強いられるなど、人道に反する強制労働を受けました。
人権侵害である以上、国家間でいかなる合意をしようとも、被害者の納得を得るものでなければ最終的解決にはなりません。被害者が解決のために何を求めているのか知る必要があります。
被害者の救済を最優先に
 (写真)三菱重工本社前で元徴用工の韓国人被害者との協議に応じるよう求める日本の支援者ら=2月13日、東京都千代田区 |
原告ら被害者の望みは何より、日本企業が人権侵害の事実を認めた上で、誠意をもって謝罪してほしいということです。韓国のみならず日本の裁判所も、強制労働の事実を認めているのだから、事実を認めることは十分に可能だと思います。
また、問題の根本には朝鮮半島に対する植民地支配の不法性の問題があります。これは引き続き検討されなければならない問題ですが、植民地支配の違法性を確認しなくとも強制労働の違法性を確認することができます。被害者の救済を最優先に、植民地支配の不法性とは切り離して、解決策を協議することはできます。
いま韓国司法による強制執行手続きが進み、日本企業の資産売却の期限が迫っています。売却が実行されれば、さらに双方で国民感情の炎上を引き起こす恐れがあります。なんとしても協議開催が急がれます。
被害者らは何度も、企業の協議の場を設けてほしいと求めてきました。しかし現在までに被告の日本製鉄(当時は新日鉄住金)、三菱重工との協議は実現していません。
補償を含め徴用工問題の根本的な解決のためには、訴訟原告同様に三菱重工などで強制労働させられた被害者全体の解決が求められています。
被害者全体との和解に向けては、(1)事実を認めて謝罪する(2)謝罪の証しとして補償する(3)再発防止のため次の世代に記憶の継承を行う―という三つの要求事項を実現することが必要です。
そのために、私は日本企業が資金を拠出して財団をつくれないかと考えています。中国人の強制動員被害に対して、西松建設や三菱マテリアルは基金を作り、いずれも協定文書に、被害の事実と人権侵害を認め、謝罪を盛り込みました。
今回も、三菱重工や日本製鉄が被害者に伝わる言葉で被害事実の認識をはっきり示してほしい。そこが一番のポイントで、解決の出発点です。財団は、謝罪の証しとして創設され、補償や再発防止の事業などを行うことになります。
このように、当事者が財団による解決を図ろうとすることに対して、日本政府が歓迎する談話を公表するなどそれに協力し支援することが望ましいです。それは、国民感情の対立まで深まっている現状を打開する一助になります。仮にそれが難しければ、少なくとも、日本企業の解決に向けた動きを妨害しないことが重要です。また、韓国政府の協力も不可欠です。韓国政府には、日韓請求権協定で曖昧な決着をし、被害者を放置してきたことへの政治的な責任がありますが、その責任を果たすべきでしょう。
大法院判決は日本の植民地支配の不法性を大きく問いました。安倍首相が判決直後から同判決に対し、「国際法違反で、ありえない」などと過剰に反応した背景には、判決をきっかけに植民地支配の問題が問われることへの強い抵抗感があったのかもしれません。
日本は植民地支配の反省について総括が不十分です。植民地支配の実態やその責任について私たちはもっと学び、事実を解明する必要があります。徴用工問題解決のための要求事項のうち、3番目の「記憶の継承」の中に、植民地支配の実態解明と、次の世代に伝える努力も含まれます。
現在の日韓関係の状況は深刻ですが、この状況が続いて幸福になる人はいません。状況をいい方向に転換するためにも、政府・議員・民間の各レベルなどさまざまなパイプを使い、協議の環境をつくらなければならないと思います。(聞き手 中祖寅一、日隈広志)