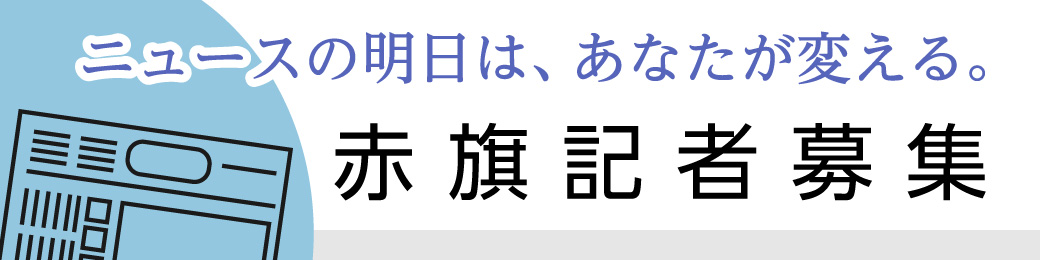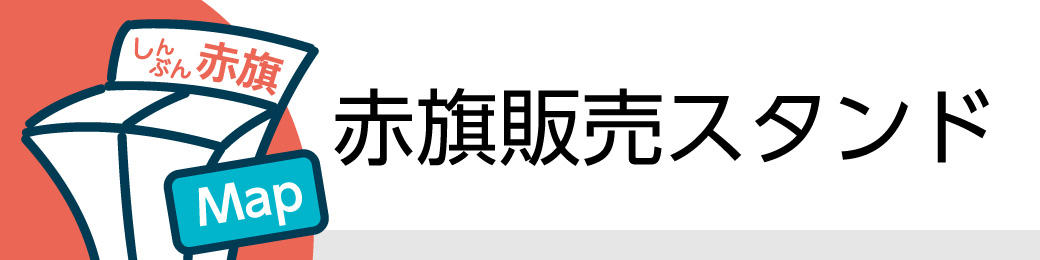2015”N3ҢҺ8“ъ(“ъ)
ӮQӮOӮPӮTҒ@ҸЕ“_ҒEҳ_“_
“ъ–{”ЕҒuҺi–@ҺжҲшҒvӮМҠлҢҜ
җ”ҒXӮМҷlҚЯҺ–ҢҸӮрҺиӮӘӮҜӮҪҒuҷlҚЯ•ЩҢмҺmҒvҒ@ҚЎ‘әҒ@ҠjӮіӮс
‘јҗlӮМҚЯӮрҢкӮзӮ№ӮйҒuҸШҢҫ”ғҺыҢ^ҒvҒ@–§ҚҗӮМҗ§“xү»ӮЕҷlҚЯӮМҠлҢҜҚӮӮЬӮй
Ғ@җӯ•{ӮНҚЎҚ‘үпӮЕҒA“җ’®–@ӮМ”НҲНҠg‘еӮЖҒA“ъ–{”ЕҒuҺi–@ҺжҲшҒvӮМ“ұ“ьӮрҗ·ӮиҚһӮсӮҫҢYҺ–‘iҸЧ–@ӮМүьҲ«–@ҲДӮМ’сҸoӮр‘_ӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBҒuҺi–@ҺжҲшҒvӮЖӮНҒAӮЗӮсӮИҗ§“xӮИӮМӮ©ҒBҗ”ҒXӮМҷlҚЯҒiӮҰӮсӮҙӮўҒjҺ–ҢҸӮрҺиӮӘӮҜӮҪҒuҷlҚЯ•ЩҢмҺmҒvӮМҚЎ‘әҠjӮіӮсӮЙ•·Ӯ«ӮЬӮөӮҪҒBҒ@Ғi–о–мҸ№ҚOҒj
Ғ@Ғ\ҒuҺi–@ҺжҲшҒvӮЖӮўӮӨҢҫ—tӮНҒA“ъ–{ӮЕӮНӮИӮ¶ӮЭӮӘӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBӮЗӮсӮИҗ§“xӮЕӮ·Ӯ©ҒH
 ҒiҺКҗ^ҒjӮўӮЬӮЮӮзҒEӮ©ӮӯҒ@ӮPӮXӮUӮQ”Nҗ¶ӮЬӮкҒB“ҢӢһ‘еҠw–@Ҡw•”‘ІҒBӮXӮQ”NҒA•ЩҢмҺm“oҳ^ҒBҺi–@ҸCҸKӮSӮSҠъҒBүәҚӮҲдҢЛ•ъүОҺ–ҢҸҒAҒuҗу‘җӮSҚҶҒvҺ–ҢҸӮИӮЗӮр’S“–ҒBҢ»ҚЭҒAҺ©—R–@‘Ӯ’cҸн”CҠІҺ–ҒA“ҜҺi–@–в‘иҲПҲхүпҲПҲх’·ҒB’ҳҸ‘ӮЙҒAҒwҷlҚЯ•ЩҢмҺmҒxҒwҷlҚЯӮЖҚЩ”»ҒxҒB |
Ғ@ҒuҺi–@ҺжҲшҒvӮНӮаӮЖӮаӮЖҒAҺ©•ӘӮМҚЯӮр”FӮЯӮй‘гӮнӮиӮЙ—КҢYӮИӮЗӮрҢyӮӯӮөӮДӮаӮзӮӨҗ§“xӮЕӮ·ҒB
Ғ@•ДҚ‘ӮМҒuҺi–@ҺжҲшҒvӮНҒA‘жӮPүсҢц”»ӮЕ”нҚҗӮӘ—LҚЯӮр”FӮЯӮкӮОҒAҸШӢ’’ІӮЧӮНӮөӮЬӮ№ӮсҒB–{җlӮӘ”ЖҚЯӮр”FӮЯӮДҚЩ”»Ӯрҗv‘¬ӮЙҸIӮнӮзӮ№Ӯй‘гӮнӮиӮЙҚЯӮрҢyӮӯӮөӮДӮаӮзӮӨҗ§“xӮЕӮ·ҒB
Ғ@Ғ\“ъ–{ӮЕӮа“ҜӮ¶җ§“xӮЙӮИӮйӮМӮЕӮ·Ӯ©ҒB
Ғ@ҚЎүсҒA“ъ–{ӮЕ“ұ“ьӮөӮжӮӨӮЖӮ·ӮйӮМӮНҒAӮ»ӮӨӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB‘јҗlӮМҚЯӮр–ҫӮзӮ©ӮЙӮөӮДҒAҺ©•ӘӮМҚЯӮрҢyӮӯӮөӮДӮаӮзӮӨҗ§“xӮЕӮ·ҒB
Ғ@•с“№ӮЕӮНҒuҺi–@ҺжҲшҒvӮЖҢДӮсӮЕӮўӮЬӮ·ӮӘҒA–@–ұҸИӮМ–@җ§җRӢcүпӮНҒu‘{ҚёҒEҢц”»ӢҰ—НҢ^ӢҰӢcҚҮҲУҗ§“xҒvӮЖҢДӮсӮЕӮўӮЬӮ·ҒB’PӮЙҒuҺi–@ҺжҲшҒvӮЕӮНӮИӮӯҒAҒuҸШҢҫ”ғҺыҢ^Һi–@ҺжҲшҒvӮЖҢДӮсӮҫ•ыӮӘӮўӮўӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB
Ғ@Ғ\ҒuҸШҢҫ”ғҺыҢ^Һi–@ҺжҲшҒvӮМҠлҢҜҗ«ӮНӮЗӮсӮИ“_ӮЙӮ ӮиӮЬӮ·Ӯ©ҒB
Ғ@“ъ–{ӮЕӮаӮұӮкӮЬӮЕҒA‘јҗlӮМҚЯӮрҢкӮйӮұӮЖӮЕҒAҺ©•ӘӮМҚЯӮрҢyӮӯӮөӮҪӮўӮЖӮМ“®Ӣ@ӮЕғEғ\ӮМҸШҢҫӮӘӮіӮкӮДҒA‘Ҫҗ”ӮМҷlҚЯӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪӮұӮЖӮНҒAӮжӮӯ’mӮзӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB
Ғ@ҺжҲшӮЖӮөӮДҗ§“xү»ҒEҚҮ–@ү»ӮіӮкӮйӮЖҒAҒuҺ©•ӘӮМҚЯӮрҢyӮӯӮөӮҪӮўҒvӮЖӮўӮӨ“®Ӣ@ӮӘӮұӮкӮЬӮЕҲИҸгӮЙӢӯӮӯ“ӯӮ«ҒAҢxҺ@ӮаӮ»ӮкӮр—ҳ—pӮөӮжӮӨӮЖҚlӮҰҒA‘{ҚёӮӘҢлӮиӮвӮ·ӮӯӮИӮиӮЬӮ·ҒB
•ДҚ‘ӮЕҢл”»ҺҹҒX
Ғ@Ғ\•ДҚ‘ӮЕӮНҒAҷlҚЯҺ–ҢҸӮМҢҹҸШӮӘҚsӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB
Ғ@•ДҚ‘ӮЕӮНӢЯ”NҺҖҢYӮвҸIҗgҢYҒA’Ұ–рүҪҸ\”NӮЖӮўӮӨ”»ҢҲӮрҺуӮҜӮҪҗl•ЁӮМӮcӮmӮ`Ң^ӮЖҒA”ЖҗlҲв—ҜӮМ‘Мүt“ҷӮ©ӮзҢҹҸoӮөӮҪӮcӮmӮ`Ң^ӮӘҲк’vӮ№ӮёҒAҷlҚЯӮӘ–ҫӮзӮ©ӮЙӮИӮБӮҪҺ–—бӮӘ‘ҠҺҹӮ¬ӮЬӮөӮҪҒB
Ғ@ӮPӮXӮWӮX”NӮ©ӮзҒAӮұӮкӮЬӮЕӮЙӮRӮOӮOҺ–—бӮр’ҙӮҰӮЬӮөӮҪҒB—\‘zӮр’ҙӮҰӮйҢл”»ӮМ‘ҪӮіӮЙҒA•ДҚ‘Һi–@ӮМҲРҗMӮНҸқӮВӮ«ӮЬӮөӮҪҒB
Ғ@ӮұӮкӮзҢлӮБӮҪ”»ҢҲӮр“ұӮўӮҪҺеӮИҸШӢ’ӮНүҪӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒBӮcӮmӮ`ҠУ’иӮЙӮжӮйҷlҚЯӢ~ҚПӮЙҺжӮи‘gӮЮҒuғCғmғZғ“ғXҒEғvғҚғWғFғNғgҒvӮМ•ЩҢмҺmӮӘ•ӘҗНӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB
Ғ@•ӘҗНҒi•Ўҗ”—vҲцҒjӮЕӮНҒAҒu–ЪҢӮҸШҢҫҒvӮӘ–сӮVӮUҒ“ҒAҒuӢ•ӢUҺ©”’ҒvӮӘ–сӮPӮUҒ“ҒAҒu–§ҚҗҺТҒiғXғjғbғ`ҒjҒvӮЙӮжӮйҸШҢҫӮӘ–сӮQӮPҒ“ӮЕӮ·ҒB
Ғ@ҒuғXғjғbғ`ҒvӮЖӮНҒu”нҚҗҗlӮМ”ЖҚsҚҗ”’Ӯр•·ӮўӮҪҒvӮЖҒA–@’мӮЕҳbӮ·‘гӮнӮиӮЙҺ©•ӘӮМ—КҢYӮрҒg— ҺжҲшҒhӮЕҢyӮӯӮөӮДӮаӮзӮӨҸо•с’сӢҹҺТӮМӮұӮЖӮЕӮ·ҒB
Ғ@•ДҚ‘ӮЕӮНҒuғXғjғbғ`ҒvӮӘҸн‘Фү»ӮөӮДӮўӮДҒA–§ҚҗӮөӮДҚЯӮрҢyӮӯӮөӮДӮаӮзӮЁӮӨӮЖҒgүaҗHҒhӮр‘ТӮҝҺуӮҜӮй—Э”ЖҺТӮӘҺы—eҺ{җЭӮЙ‘Ҫҗ”ӮўӮйӮЖҺw“EӮіӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB“ъ–{ӮЕ“ҜӮ¶ӮұӮЖӮӘӢNӮ«ӮДӮаӮЁӮ©ӮөӮӯӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB
ҢxҺ@ӮМҲб–@’®Һж
Ғ@Ғ\“ъ–{ӮЕӮНӮЗӮӨӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒB
Ғ@–іҺАӮМҗlӮӘ–§ҚҗӮЙҠӘӮ«ҚһӮЬӮкӮйҷlҚЯҺ–ҢҸӮН“ъ–{ӮЕӮа‘ҪӮӯӢNӮ«ӮДӮўӮЬӮ·ҒB
Ғ@•ДҚ‘ӮМғXғjғbғ`ӮЙҺ—ӮҪҺ–—бӮЕӮНҒA–kӢгҸBҺsӮЕӢNӮ«ӮҪҲш–мҢыҺ–ҢҸҒiӮQӮOӮOӮS”NҒjӮӘӮ Ӯ°ӮзӮкӮЬӮ·ҒB
Ғ@•ъүОҺEҗlҺ–ҢҸӮМ”нӢ^ҺТӮЙӮіӮкӮҪҸ—җ«ӮjӮіӮсӮӘҒA‘г—pҠДҚ–ӮЕ“Ҝ–[ӮМҸ—җ«ӮlӮЙҒuҺсӮрҺhӮөӮҪҒv“ҷӮЖҒg”ЖҚsҚҗ”’ҒhӮөӮҪӮЖӮўӮӨҺ–ҢҸӮЕӮ·ҒB
Ғ@“Ҝ–[ӮМҸ—җ«ӮlӮНҒA‘Ҫҗ”ӮМҗЮ“җӮЖҠoӮ№ӮўҚЬҺж’ч–@Ҳб”ҪӮЕ‘Я•ЯӮіӮкҒAҺАҢYӮЖӮИӮйӮұӮЖӮр”сҸнӮЙӢ°ӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBҺ©җgӮМҗЮ“җӮИӮЗӮЕҒAҢxҺ@ӮӘҺжӮи’ІӮЧӮҪӮМӮНҒAӮнӮёӮ©ӮS“ъҒBӮjӮіӮсӮМ–[“аӮЕӮМҢҫ“®ӮЙӮВӮўӮДӮМҺ–Ҹо’®ҺжӮНҒAӮTӮV“ъӮЙӮМӮЪӮиӮЬӮ·ҒB
Ғ@ӮjӮіӮсӮН–іҚЯӮЖӮИӮиӮЬӮ·ӮӘҒAҢxҺ@ӮНӮlӮрҲУҗ}“IӮЙғXғpғCӮЖӮөӮД“Ҝ–[ӮЙ“ьӮкҒA”ЖҚsҚҗ”’Ӯр•·Ӯ«ҸoӮ»ӮӨӮЖӮөӮЬӮөӮҪҒBҚЩ”»ҠҜӮНӮlӮрҺgӮБӮҪ’®ҺжӮНҲб–@ӮЖ”»’fӮөӮЬӮөӮҪҒB
Ғ@Ғ\ҒuҸШҢҫ”ғҺыҢ^Һi–@ҺжҲшҒvӮН–§ҚҗӮМҒgҗ§“xү»ҒhӮЖӮўӮҰӮЬӮ·ӮЛҒB
Ғ@ӮұӮМҗ§“xӮӘҒAҠлҢҜӮҫӮЖӮўӮӨ”FҺҜӮН—§–@ҺТ‘ӨӮЙӮаӮ ӮиӮЬӮ·ҒB
Ғ@–@җ§җRӮНҒAҢлӮБӮҪ–§ҚҗӮр–hӮ®‘[’uӮЖӮөӮДҒuӢ•ӢUӢҹҸqҚЯҒvӮрҗЭӮҜӮйӮЖӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮкӮН‘{ҚёҠҜӮМ‘OӮЕҒA‘јҗlӮМҚЯӮЙӮВӮўӮДғEғ\ӮМӢҹҸqӮрӮөӮҪӮзҸҲ”ұӮ·ӮйӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮ·ҒB
Ғ@Ңъҗ¶ҳJ“ӯҸИӮМ—X•Ц•sҗіҺ–ҢҸӮЕӮНҒA‘ә–ШҢъҺqӮіӮсӮМҸгҺiҒA•”үәӮзӮНҒu‘ә–ШӮіӮсӮМҺwҺҰӮӘӮ ӮБӮҪҒvӮЖҒA‘еҚг’nҢҹ“Б‘{•”ӮӘҚмҗ¬ӮөӮҪ’ІҸ‘ӮЕӮМӮЧӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮЖӮұӮлӮӘ–@’мӮЕӮНҒA‘ҠҺҹӮўӮЕ’ІҸ‘ӮМ“а—eӮрӮӯӮВӮӘӮҰӮөӮЬӮөӮҪҒB
Ғ@ҒuӢ•ӢUӢҹҸqҚЯҒvӮӘӮ ӮйӮЖҒA‘{ҚёҠҜӮМ‘OӮЕҸШҢҫӮөӮҪӮұӮЖӮр•ўӮөҒA–@’мӮЕҗ^‘ҠӮрҢкӮБӮҪӮұӮЖӮӘҸҲ”ұӮМ‘ОҸЫӮЖӮИӮБӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒBӢҹҸqӮөӮҪҗlӮМҢыӮрҢЕӮЯӮДӮөӮЬӮӨӮұӮЖӮЕҒAҷlҚЯӮМҠлҢҜӮрҚӮӮЯӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒB
Ғ@Ғ\•ЩҢмҺmӮНҒAӮЗӮсӮИ—§ҸкӮЙ’uӮ©ӮкӮЬӮ·Ӯ©ҒB
Ғ@–§ҚҗӮр–hӮ®Һ•Һ~ӮЯӮЖӮөӮД–@җ§җRӮНҒA‘јҗlӮМҚЯӮрҳbӮ·‘ӨӮМ•ЩҢмҗlӮМҚҮҲУӮр•K—vӮЖӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB
Ғ@ӮөӮ©ӮөҒA•ЩҢмҗlӮЙӮөӮДӮЭӮкӮОҒAҲЛ—ҠҺТӮМҳbӮӘ–{“–ӮИӮМӮ©Ӣ•ӢUӮИӮМӮ©”»’fӮөӮжӮӨӮӘӮИӮўҒB•ЩҢмҗlӮӘ”ВӢІӮЭӮЙӮИӮБӮДӢкӮөӮЮӮұӮЖӮӘ—eҲХӮЙ‘z‘ңӮЕӮ«ӮЬӮ·ҒB
Ң —НӮЙӮжӮйҲ«—p
Ғ@Ғ\Ң —НӮЙӮжӮйҲ«—pӮНҚlӮҰӮзӮкӮЬӮ·Ӯ©ҒB
Ғ@—бӮҰӮОҺs–Ҝ’c‘МӮЙҢxҺ@ӮМ‘{ҚёҲхӮрҗц“ьӮіӮ№ӮДҒAҒu“Б’и”й–§Ӯр“ьҺиӮөӮжӮӨҒvӮЖҒuӢӨ–dӮөӮЬӮөӮҪҒvӮЖ–§ҚҗӮіӮ№ӮЬӮ·ҒB–§ҚҗӮөӮҪ‘{ҚёҲхӮНҒAҒuҸШҢҫ”ғҺыҢ^Һi–@ҺжҲшҒvӮЕҒA•sӢN‘iӮИӮЗҢyӮўҸҲ•ӘӮЕӮ·ӮЬӮ№ӮйҒB
Ғ@Ҳк•ыӮЕ’c‘МӮМ‘јӮМғҒғ“ғoҒ[ӮЙӮВӮўӮДӮНҒA“Б’и”й–§•ЫҢм–@ӮМӢӨ–dҚЯӮЕҸd”ұӮрҺуӮҜӮйӮЖӮўӮӨҺ–‘ФӮаҚlӮҰӮзӮкӮЬӮ·ҒBӮPӮXӮTӮQ”NӮЙ‘е•ӘҢ§ӮЕӢNӮ«ӮҪҗӣҗ¶ҒiӮ·ӮІӮӨҒjҺ–ҢҸӮЕӮНҒA“ъ–{ӢӨҺY“}ӮЙҗЪӢЯӮөӮҪҢцҲАҢxҺ@ҠҜӮӘҢр”Ф”ҡ”jҺ–ҢҸӮМҚЯӮрӢӨҺY“}ҲхӮЙүҹӮөӮВӮҜӮжӮӨӮЖӮөӮЬӮөӮҪҒBӮұӮӨӮөӮҪүЯӢҺӮМҺ–ҢҸӮ©ӮзӮаҲ«—pӮНӮ ӮиӮҰӮйӮұӮЖӮЕӮ·ҒB
Ғ@”й–§•ЫҢм–@ӮЙүБӮҰӮДҒA“җ’®–@Ҡg‘еӮвҸШҢҫ”ғҺыҢ^Һi–@ҺжҲшҒAӮіӮзӮЙӮНӢӨ–dҚЯӮӘғZғbғgӮЙӮИӮйӮЖҒAҗӯ•{ӮЙӮЖӮБӮД’eҲіӮМӢӯ—НӮИ•җҠнӮЙӮИӮйӮұӮЖӮНҠФҲбӮўӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB
Ғ@ҸШҢҫ”ғҺыҢ^Һi–@ҺжҲшҒ@–@җ§җRӢcүпҒuҗVҺһ‘гӮМҢYҺ–Һi–@җ§“x“Б•К•”үпҒvӮӘҚр”NҒA“җ’®–@ӮМҠg‘еӮЖҚҮӮнӮ№ӮД’сҲДӮөҒAҚЎ”NӮМ’КҸнҚ‘үпӮЕӮМ–@җ§ү»ӮрӢҒӮЯӮДӮўӮЬӮ·ҒBҷlҚЯҺ–ҢҸӮӘ‘ҠҺҹӮ¬”ӯҠoӮөӮҪӮұӮЖӮрҺуӮҜӮД”ӯ‘«ӮөӮҪ“Ҝ•”үпӮН“–ҸүҒAҺжӮи’ІӮЧӮМ‘S–КүВҺӢү»ӮрҸЕ“_ӮЖӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©Ӯө•”үпӮНҒAүВҺӢү»ӮМ‘ОҸЫҺ–ҢҸӮрҒA‘SҺ–ҢҸӮМ–сӮQҒ“ӮЙӮЖӮЗӮЯӮй•sҸ\•ӘӮИӮаӮМӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB